神戸大学大学院理学研究科の東晃輔 大学院生(研究当時、現:東レリサーチセンター勤務)、分子フォトサイエンス研究センターの岡本翔 助手(研究当時、現:筑波大学助教)および小堀康博 教授、長崎大学大学院総合生産科学研究科(工学系)の作田絵里 教授、新潟大学大学院自然科学研究科の生駒忠昭 教授、名古屋大学大学院情報学研究科の東雅大 教授らの研究グループは、ドイツのザーランド大学との共同研究により、人体に無害な長波長光を高いエネルギーをもつ短波長光に変換するアップコンバージョン過程の中間体が、分子内部の励起子ホッピング運動を1兆分の1秒の単位で繰り返し起こす現象を明らかにしました。このホッピング速度は溶媒の粘性を変えるだけで大きく変化させることが可能で、それにより光の波長変換の効率を制御できることを示しました。
今後は、分子振動を巧みに利用する光エネルギー変換デバイス開発が進展し、人体に害のない近赤外光を利用する光線力学的ながん治療や、その細胞内部のミクロな流体環境センシングへの応用など幅広い分野への展開が期待されます。
この研究成果は、2025年5月19日に、独国科学雑誌「Angewante Chemie International Edition」に掲載されました。
https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2025/06/post-835.html
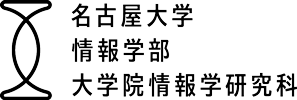
 在学生の方へ
在学生の方へ  教職員の方へ
教職員の方へ 